<D>
前回のもろみがこんなに増えましたよ。
<T>
発酵がすすみ、こんなに泡が高くなってるんですね。
そういっている間にもぶくぶくしていますが、この上に取り付けられている機械はなんですか?
( 真中で細い針金のようなものがまわっている)
 
<D>
発酵がすすむと泡が高くなります。これを高泡(たかあわ)といいます。
高泡の状態では泡があふれてしまうので、機械で泡を消すんです。
そしてさらに発酵がすすむと泡は低くなり(落泡[おちあわ])、
最後には 泡は無くなります(地[ぢ])。
 |
 |
| 留後10時間 米が水を吸って膨らんできた |
留後5日目 泡が立ち始めてきている |
 |
 |
| 留後8日目 高泡 |
留後18日目 落ち泡 |
<T>
泡は触るだけで消えるんですね。

<D>
毎日、朝と晩の2回、櫂(かい)を使ってもろみを撹拌(かくはん)します。
これを『櫂入れ』と言います。
櫂入れは、ただ混ぜるのではなく、もろみ全体を均一に混ぜます。
この時、櫂を入れ過ぎると雑味の多い酒になってしまいます。逆に櫂が入り足らないと発酵が上手く進みません。微妙な加減が必要なんですよ。
<T>
発酵の具合はどうして分かるんですか?
<D>
毎朝、櫂入れを行った後、分析をするんですよ。
<T>
分析?
<D>
酒造りは、麹菌の酵素による糖化と酵母による発酵の微妙なバランスによって成り立っています。(並行複発酵)
この麹菌と酵母は、肉眼では見ることの出来ない小さな生き物(微生物)です。
そのため、泡などの状態だけでなく、科学的な分析も行なってもろみを管理します。
分析は、日本酒度・アルコール度・酸度・アミノ酸度・直糖・pHの測定を行ないます。
その他に、顕微鏡を使って酵母や乳酸菌などの微生物を観察します。
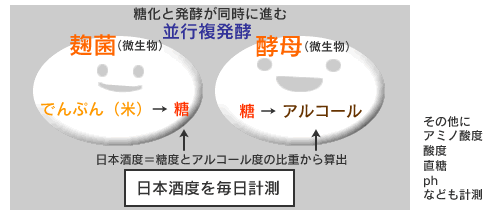
糖化によって[でんぷん→糖]、発酵によって[糖→アルコール]となります。
アルコール度というのは、発酵によりできるアルコールの比重を調べ、
算出するものです。
 
<T>
麹はでんぷん(米)を糖に変え、酵母は糖をアルコールに変えるんですよね。
その発酵の具合を毎日確認するということですね。職人の勘だけではなく
さらにデータによる管理によって、品質が保たれているというわけですね。 |